ぼくが子どものころ、ほしかった親になる。
『ぼくが子どものころ、ほしかった親になる。』を、先日仙台に行った際の新幹線車内で読み終えました。写真家にして狩猟家でもある著者の幡野広志氏は、34歳で多発性骨髄腫というガンを患い、余命3年を宣告された方です。本書は、そんな著者が一人息子を思って書き記したもので(出版は今年8月)、たまたま書店で手に取った時に共感できるフレーズを見かけたものだから、後日Kindle版を買っていたのです。いくつか引用すると、たとえば
「誰とでも仲良くする方法」ではなくて「嫌な人への対処法」を教えたいし、それが子どもに役立つ親の悪知恵だと思う。
というのは全くもってその通りだと思いました。そもそも自分は「誰とでも仲良くする方法」なんて知らないし、当然実践もしていないけれど、それより苦手な人と接しなければならない、うまく折り合いをつけなければいけない時に、どう振る舞うかという方が遥かに大事だと思っていて、そういうことについて何か役立つアドバイスができたらいいなと思います。いつ、どんな環境に身を置こうとも、そういう苦手な人は必ずいるものだから。
おなかがすいている人には、魚を上げるより釣りを教えたほうがいい。子どもにお金を残すより、子ども自身がお金を生み出す方法を教えたほうがいい。
これも全くそう。受験環境に揉まれるうち拙速かつ安易に正解ばかり欲しがるようになっては困るのに似て、方法論とか手法、プロセスそのものを身につけ、何が本当の正解か、後悔の少なさそうな選択肢は何か、ちゃんと自分で考え判断できるようになって欲しいなと思うし、むしろ何を選択をしようと、どうすれば自ら出した答えを正解にできるかみたいなことまで教えられると良いのだけど。加えて、人の生き死にに関して
僕は自殺を否定しないし、安楽死を含めて、死は絶望した人のオプションだと思っている。本人が死にたいほど苦しみ、決心して決めたのだ。その先のその人の人生に責任が持てないのであれば、止める権利はないだろう。そして、誰かの人生に誰かが責任を持つなんて、夫婦でも親と子でも、できないことなのだと思う。
とか
「長く生きてほしい」という気持ちは善意だし、僕だって妻や息子が病気になったら同じことを思うかもしれない。その気持ちを繙いていくと、「自分が悲しみたくない」というところに着地する。自分が悲しみたくないから、死んでほしくない。本人の幸せを考慮したものではなく、実は利己的だったりするのだ。
とあったのは、諸手を挙げて賛同とまでいかずとも、まぁまぁ分かるお話だなと感じました。基本的には誰の死をも望んだりなんかしないし、身内であれば尚更だけど、死を巡っては途端にその人の気持ちを慮ることが複雑でややこしく思えることがあって、難しいなと。相手の人格なり人生を尊重しようと思えば思うほどに、例えば自死の選択を認めざるを得ない気持ちにすらなりますが、どこかでやっぱり納得できない、腑に落ちないところはあって。それを利己的だと言われれば、確かにそうかもしれないけど。かくも人が人に寄り添うことが難しく思えてしまうだなんて、自分自身を含め、人間ってままならないものですね。
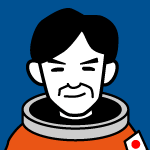 @kazuhitoは、木達一仁の個人サイトです。主に宇宙開発や人力飛行機、Webデザイン全般に興味があります。Apple製品と麺類とコーヒーが好きです。南極には何度でも行きたい。アクセシビリティおじさんとしてのスローガンは「Webアクセシビリティ・ファースト」。
@kazuhitoは、木達一仁の個人サイトです。主に宇宙開発や人力飛行機、Webデザイン全般に興味があります。Apple製品と麺類とコーヒーが好きです。南極には何度でも行きたい。アクセシビリティおじさんとしてのスローガンは「Webアクセシビリティ・ファースト」。